隠居たるもの、いつだって最後に残るは読書感想文。2025年8月24日夕刻、風呂に入る前おもむろにFBを開けてみると「この春に小学校に入学したばかりの娘があと一週間を残して夏休みの宿題をすべてやり終えた!あとは心ゆくまで遊ぶのみ!」と宇都宮で暮らす姪がアップしていた。誇らしげな顔をしているであろう姪孫を「なかなか感心である」と思い浮かべつつ、それと同時に「もう夏休みは終わっちゃうのか」などと我が身のことのように寂しい心持ちを抱えたりもする。そもそもが「毎日が夏休み」といって過言でないぷらぷらした暮らしをしているくせに勝手なものである。しかし朝のニュースを見れば熱中症への警戒が連呼されるほどに酷暑はいまだ一向に衰えるそぶりもない。その一方で冬が早く始まるここ白馬の子どもたちの夏休みはお盆休みとともにすでに先週に終わっており、気がついてみれば夜はすっかり虫の音に包まれている。やはり「もう夏休みは終わる」のである。

夏休みの読書感想文
今になって小学生のころを想い起こしてみると、夏休みの宿題の中でいつも最後に残るのが原稿用紙2枚の読書感想文だった。算数や国語のドリルは開きさえすればそのまますぐに進められるのだが、読書感想文ばかりは本を読まない限り手をつけられない。夏休み中おおむね遊び呆けていた私なぞは「あと一週間」の声を聞いて慌てて本を探して手に取ったものだ。読み終えられないままやっつけ仕事のようにでっち上げたことだってある。幼少のみぎりよりこうして刷り込まれた教育の賜物か、それとも宿題にきちんと取り組まなかったことへの今さらながらの贖罪か、大人になってからも「せっかくの夏だ、本を読もう」と必ず意識する。そこには、まとまった休みが取れるのは盆暮正月のみで、とはいっても暮と正月はやることも多くせわしなく、となるとゆっくり腰を落ち着けて読書できるのは盆のみ、といった事情が潜んでいたことも忘れてはいけない。しかし今の私の暮らしに照らしてみれば、夏であれ冬であれ季節は関係ない。ところが2025年の今だからこそ、「夏には読書」と考える具体的な理由が明確に存在するのである。ほぼ毎朝にニュースで警告が発せられているではないか、あまりにも危険で無闇矢鱈に外を出歩いたりしてはいけないのだ。だからこそ私は7月と8月はジムも休会し一年のうちで完全に身体を休める期間に充てる。そして涼しい部屋に座ってじっくりと本を読む。

「戌井昭人 芥川賞落選小説集」
戌井昭人(いぬい・あきと)という1971年生まれの作家を知ったのは熊本でのことだった。いつものごとくつれあいの実家、義父母へのご機嫌うかがいに梅雨のさなか6月に訪れ、これまたいつものごとく時間を見繕って街に繰り出し、熊本ラーメンをすすって上通の長崎書店に足を運ぶ。地方都市の古くからある小さな店ではあるが、ここは陳列棚を見るだけでも心が躍る日本有数の気骨あふれる書店なのだ。イギリスのパンクな批評家マーク・フィッシャーに出会ったのもここの人文コーナーでのことだった。そしてこの6月に見つけたのが平積みになっていた「戌井昭人 芥川賞落選小説集」である。
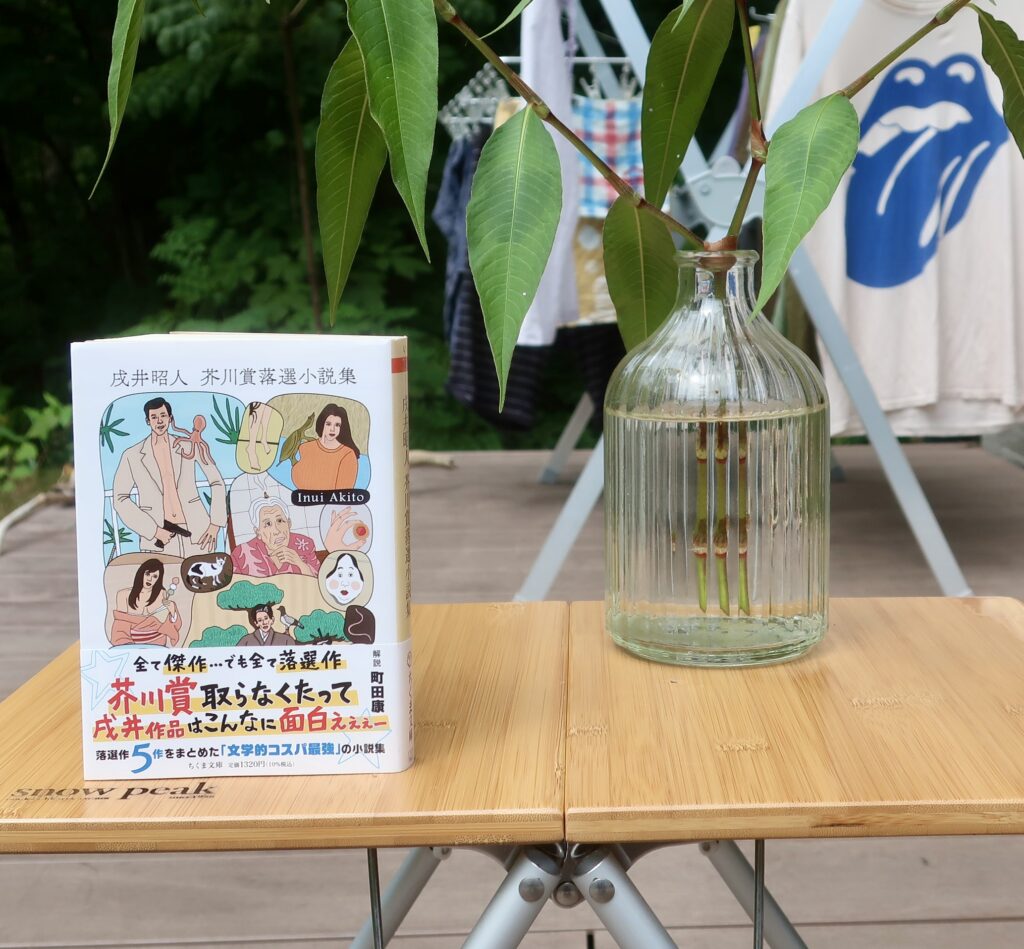
それにしても長崎書店、平積みである。よりによって「落選小説集」なのに平積みである。しかも帯は町田康である。手にとってパラパラ立ち読みしてみると、戌井昭人は2009年から2014年の間に5回も芥川賞候補になって5回とも落選したのだという。そしてこのたび、その落選作をすべて集めて458ページの文庫本にしたというのである。そのまま戻すのがしのびなく買い求めた。そしてお盆休みが過ぎたあとからようやく読み始め、姪孫が夏休みの宿題をすべて終えるのと同時に読み終えた。これがまたとんでもなく面白かった。

芥川賞は「もらう」ものなのか「とる」ものなのか
この本のあとがきの中で、戌井昭人は「公募でない以上、芥川賞は『とる』ものでなく『もらう』もの」といった趣旨のことを書いているが、落選第5作目となる「どろにやいと」について「こうなったら芥川賞を意識しまくって、過去の受賞作品にあえて影響を受けまくって、書いてみようと考えた」と自ら解説している通り、芥川賞には「傾向と対策」がある。もちろんそのすべてではないけれど、リアルタイムでというならば49年前の村上龍の「限りなく透明に近いブルー」からほぼ半世紀にわたって(それ以前の受賞作だって受賞者がのちに大家となっていれば後追いで目を通し)読んでいるのだからして素人ながらなんとなく察しはついている。まず「適切な枚数」が必須条件。受賞後に文藝春秋に一挙掲載される都合上、その紙面構成に支障をきたすほどに短かいもの長いものは「晴れて受賞作」とはならない。そしてどちらかといえば「現代性をまとったエキセントリックな状況の中でアイデンティティーが揺らぐ」といったテーマの作品が好まれる。そうした「傾向と対策」を熟知した上で「狙って書いたな」と感じられる受賞作も垣間見られ(あくまで個人的感想であるが)、その都度その「小賢しさ」が鼻につき「興醒め」な気分を禁じえないことも少なくはない。初めて接する戌井昭人の落選5作品にはそうしたものをいっさい感じなかった(さすがに「意識した」という「どろにやいと」には少し匂うものの🤭)。だから受賞できなかったのかもしれないが、それがなんとも痛快ではある。

彼が描く主人公たちは会社に勤めてもいなければ完全なアウトローでもない。どっちつかずのその隙間で、身も蓋もない劣情を抱えながら、どちらかというと自堕落に生きている。熊本の書店で初めて知ったとはいえ、そもそも戌井昭人と私は生まれ育った地域が近い。作品の舞台となるのも東京は荒川区の南千住や三ノ輪、そして台東区の吉原から浅草を抜けて上野に至るあたりだ。私が育った隅田川を挟んだ墨田区側も含め、この地域には実のところどっちつかずのその隙間で生きている人が多かった。その空気感がなんとも懐かしい。そんな主人公たちにちょっとしたさざなみが起きて否応なしに話が動き出す。だからといって身も蓋もない劣情はことあるごとにひょっこり顔を出すし、ピンチに際して眠っていた本能が呼び醒まされるなんてこともない。つまりフィクションであるから嘘なんだけれども、とってつけた嘘がない。だからこそ作中に浮かび上がる悲喜こもごもな瞬間がしみじみそれとして味わえる。浅草の鷲神社(おおとりじんじゃ、酉の市の起源発祥の神社)の静かな境内で、主人公とりっちゃんが寄り添う「ぴんぞろ」という作品のラストなぞ白眉である。
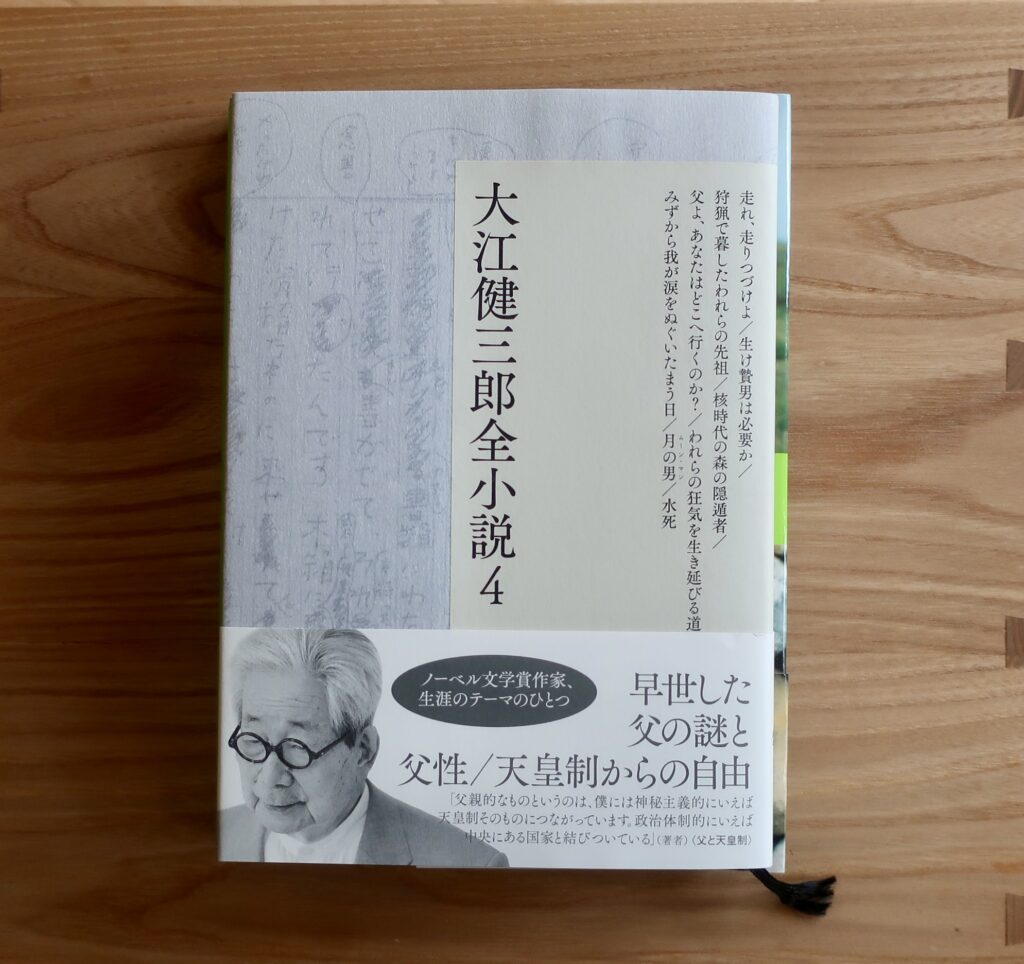
その他の夏の課題図書
つまり戌井昭人の落選5作品は「枚数的にはピッタリなんだけど芥川賞が望むテイストではない、しかし小説的にはとても優れているのでノミネートくらいはしておかないと芥川賞の権威に疑義を持たれてしまう」という打算から候補となり落選したのではないかと推察する次第。つまり芥川賞には収まりきらないのである。そして「なにも夏に読んだ本はこれだけではない」ことを証するためあと一冊だけ、この夏を通して手にしていた本を紹介しよう。死ぬまでに読破しようと試みている「大江健三郎全小説」15巻中のその4だ。腰を落ち着けて読書に取り組める時期以外に読みようがない、上下二段に印刷された638ページ。こちらは芥川賞受賞者だが、違った意味で芥川賞的範疇に収まらない不世出の大小説家である。そのテーマ設定、ほとばしるその知性、ごつごつしていて読みづらいのに鷲掴みにしたまま離してくれないその文体、相変わらず打ちのめされる。文学てえのはこんな人もいればあんな人もいるから面白い。

今日8月26日の朝のこと、ここ白馬では珍しいことに救急車のサイレンが鳴り渡った。朝食を食べながら窓の外を見やると、すぐ近所のお宅の前で音を消した赤いサイレンが回転している。そのうち警察車両も何台か駆けつけてきた。隣人として話をしてみると、普段から一人でここで暮らしておられるひと回りほど年上と思しきご婦人が亡くなったのだという。「事件性はまずなさそう」とのことだが、もちろん挨拶もすれば、雪かきのときに声を掛け合うご近所さんでもあったからショックを禁じえない。戌井昭人の作品にそうあるように、往々にして人というのは唐突にあっけなく死んでしまうことがある。この間のお盆休みに、娘さんが孫を連れて久しぶりに遊びに来ていたことがせめてもの救いというかなんというか…。ご冥福を祈るばかりだ。ああ、もうすぐ隠居の身。悲喜こもごもな瞬間というのはこうしてまた訪れるのだ。
