隠居たるもの、自由な世界でロックし続けろ。2025年3月15日、私たち夫婦とドイツ語Q組の友だち、3人合わせて181歳となる初老の一行は、頭上を走る新交通ゆりかもめのレールを見上げながら、豊洲PITに向かって歩いていた。2014年にできたこのライブハウスに足を運ぶのはなにを隠そう初めてのこと。最寄駅は新交通ゆりかもめの新豊洲駅と案内されたのだが、いかんせんこの新交通、運賃が高い。都バスに乗る私たち夫婦と東京メトロ有楽町線を使うドイツ語Q組の友達、ともにまずは豊洲駅に降り立つ。そこからゆりかもめに乗り換えたとして、新豊洲はひと駅先で乗車時間はたったの1分、かかる運賃はICカード使用時で189円。そこから徒歩3分という触れ込みだが、豊洲駅からそのまま歩いたところでせいぜい徒歩12分。乗り換えに要する時間やらもろもろを考え合わせれば大した差も生じまい。私たちは迷わず豊洲駅で待ち合わせ、歩いて向かうことにしたのだった。

「お兄ちゃん、ライブの後に寄ってちょうだいね」
「整理番号1820番台までの方!」午後7時開演に合わせ午後6時30分に到着してみると、まだ入場を許可されない群衆が会場の前にむらがり自分の順番が呼び出されるのを待ちわびている。ここのキャパシティはオールスタンディングで3,100人ほど、この日のチケットは完売、私たち夫婦が持つチケットの整理番号は1,860番台で友達はぴったり2,150番、一緒に入場することにしてしばし聞き耳を立てる。しかし日本にオールスタンディングで3,000人を超えて収容できる「箱」が現れるなんて、ドキドキしながら初めてライブハウスに足を踏み入れたあの時には想像すらできなかった。あれはもう少しで16歳というまだまだいたいけな春のこと、センター街に入ってすぐの雑居ビルの4階か5階にあった渋谷屋根裏、あらかた45年前に遡る。すぐ下にキャバレーロンドンがあって、エレベーターなんかないから階段を使って上がる途中、胸元もあらわなホステスさんに「お兄ちゃん、ライブの後に寄ってちょうだいね」なんてよくからかわれたものだ。まさに隔世の感、当時のライブハウスなんてものはいかがわしい空気が漂うアングラな溜まり場、メジャーなところでいえばRCサクセションもステージに立ったその屋根裏だって、300人も入って押し合いへし合いすれば、たちまち酸欠になるようなそんな広さしかなかった。
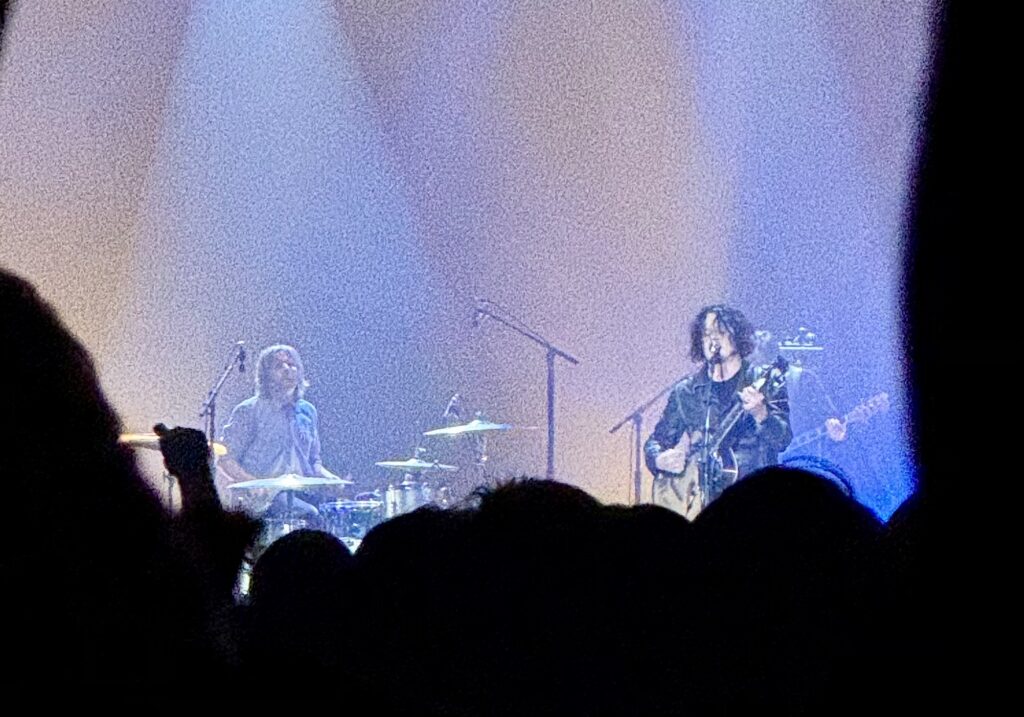
いつだって信用できる男、その名はジャック・ホワイト
ジャック・ホワイトは1975年7月生まれ、本当は夫婦なのに表向きは姉弟と言い張っていたメグと結成したザ・ホワイト・ストライプスで21世紀早々にブレイクし、その後ザ・ラカンターズやザ・デッド・ウェザーなどのバンドを経て今はソロ名義、四半世紀の間ずっと第一線で活躍するもう少しで50歳になるミュージシャンだ。それぞれのキャリアでおそらくこれまでに合計5回ステージを観てきたが、とにかく信用できる。まずもって自分が影響を受けた初期デルタ・ブルースやハードロックに対する敬意を常に忘れず、いつだってテンション高く情熱に溢れていて、ステージで手を抜いている様子を目にしたことがない。だから終演後に感嘆のため息が漏れなかったこともない。この日だってそうだった。一方で愛する音楽の継承発展のためと、レコードのプレス工場も持つ会社 サード・マン・レコードを立ち上げ、規模を拡大し大きな成功を収めてきた堅実な青年実業家の顔も持つ。そして何よりおそれることなく直言する硬骨漢でもある。
「オレンジ色のクソゴリラ」
上にアップしたロック史に残るアンセム「Seven Nation Army」を、大統領選挙運動中にトランプ陣営がジャックに断ることなく使用した。ジャックは「ファシストども、勝手に俺の曲を使うんじゃねえ!」と激怒。そのトランプが大統領になった今も「オレンジ色のクソゴリラとオリガルヒになろうとしている電気自動車会社の、選挙に出馬したこともない、公職に就いたこともない、兵役に一日も就いたこともない男」と真っ向から歌う。来日直前のステージをレポートするそんな記事を読んで、「なるほど、ゴルフ焼けした彼はアメリカ人にもオレンジ色に見えるんだ」とか、「そりゃあ有能な経営者であるジャックからしたら今までに6度も破産しているくせに臆面もなく『ディールが得意なビジネスマン』なんて顔する嘘つきなんざちゃんちゃらおかしいわな」とか、「たしかに独裁者にピタッとくっついて私服を肥やしたロシアのオリガルヒと何ら変わりゃしないね、ありゃ」などと感心したもんだが、残念なことその曲が演奏されることはなかった。その代わりというにはあまりにあまり、アンコールの一曲目に「Rock’in the free world」を演奏し始めたもんで、「こりゃ一本とられた、その手があったか!」と膝をうったのである。

ニール・ヤングはいつだって怒っている
今年の秋に80歳を迎える御大ニール・ヤングはいつだって怒っている。トランプがウクライナのゼレンスキー大統領をわざわざホワイトハウスに呼び出し愚弄したあのときなんか沸点に達したに違いない。6月18日にスウェーデンで開始されるヨーロッパツアーに先立ち、ウクライナでフリーコンサートを開催することを即座に発表した。さすがに日々刻々と変化する戦時下での「安全性」を鑑み開催は断念されたが、その瞬発力たるやいささかも衰えていない。ジャックがアンコールで演奏した「Rock’in the free world」、このニール・ヤングが1989年に発表した有名な曲だ。しかも、シカゴカブスの熱狂的なファンで開幕戦を観戦するためたまたま東京を訪れていた、御大ニールとの縁も深いグランジの雄 パール・ジャムのエディ・ヴェイダーをゲストに呼び込み歌われた。その筋の人からしたらこいつはけっこう「大事件」だったのである。
自由な世界でロックし続けろ
「Keep on rock’in the free world」という象徴的なコーラスの部分しかこの曲について記憶に留めていない多くの人は、無条件に「自由主義」を礼賛する能天気なアンセムだと勘違いしている。だからトランプも選挙運動でこの曲を勝手に使い、やはりニールを怒らせた。しかし最初から歌詞をきちんと読み込んでみると(そもそもトランプ支持者で歌詞をきちんと読み込む人なんてそうそういないのだろうが)、彼は「自由の名の下に強欲と無法と野蛮が蔓延るこの社会、そこから弾き出された者たちにはせいぜいロックを聴いて踊ることくらいしかできやしない、だから自由な世界でロックし続けろ」と皮肉に歌い、新自由主義を痛烈に告発しているのだ。もちろん今でもその意味合いは高まってはいても減じてはいない。それに加えてあらためて、強欲と無法と野蛮から発せられる嘘を、嘘だと知りつつ、多くの人がその嘘を受け入れるという新しい現象によって、「自由主義国」が抑圧的な社会へと急速に歪みつつある今日、文字通り自由を高らかに求めるアンセムとしての役割が、この曲には重ねて付与されているのである。

「ロック小僧がそのまま大人になった感じだね」、終演後に豊洲駅近くの四川料理店で汗をかきながら、ドイツ語Q組の友だちがジャックを評してそう言う。本来いっしょに来るはずだった近所の友だちに抜き差しならない用事が持ち上がり、ピンチヒッターとして急遽チケットを引き取ってくれたギター弾きの彼、すっかりジャックのファンになったようだ。二人が大学生だったほぼ40年前のあのあたり、連れ立って小さくていかがわしいライブハウスによく行ったものだ。ジャック・ホワイトにこれだけ感動するんだから、私たちだって「ロック小僧のまま還暦を迎えた感じ」だろう。ああ、もうすぐ隠居の身。自由な世界でロックし続けようぜ。
